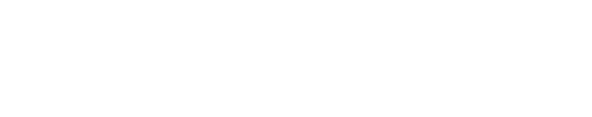フレイルの原因や予防方法とは?3つの柱や食事のちょい足しまで詳しく紹介
2019年に策定された「健康寿命延伸プラン」の取り組みの1つとして「フレイル対策」が挙げられたことをきっかけに、自治体や医療・介護の現場ではフレイル対策が取られるようになってきました。
本記事では、フレイル対策に携わる方のために、フレイルについて詳しくお伝えするとともに、フレイル対策の基本や、実際の取り組み事例についてご紹介します。
フレイルとは?
フレイルとは?
まずは、フレイルについて正しい知識を持ちましょう。フレイルやその原因について解説します。
フレイルとは健康な状態と要介護状態の中間の段階
「フレイル」とは、高齢者が加齢に伴って心身の活力(筋力や認知機能、社会的つながりなど)が低下し、健康障害や要介護状態に陥る危険性が高まっている状態を指します。2014年に、日本老年医学会が提唱した概念です。
健康な状態と要介護状態の中間にあたり、適切な介入によって要介護状態への進行を予防できる可逆性があるため、フレイル予防が重視されています。
【フレイルの3要素】
・身体的フレイル:筋力や運動機能の低下
・認知的(精神・心理的)フレイル:うつ状態や軽度の認知機能低下
・社会的フレイル:社会との繋がりの希薄化、経済的困窮
フレイルと似たような言葉として、サルコペニアやロコモティブシンドロームがあります。サルコペニアは、加齢による筋肉量の減少で筋力や身体能力が低下した状態です。ロコモティブシンドロームは、運動器の障害の影響で移動機能が低下した状態を指します。いずれも、身体的フレイルの一部です。
フレイルの原因
フレイルに陥る原因は、1つではありません。様々な要因が複合的に関わり合い、フレイルが起こります。たとえば、原因として次のようなものが挙げられます。
・活動量の低下
・他者との交流機会の減少
・筋力低下
・疲れやすさ
・慢性疾患(呼吸器疾患、心血管疾患など)
・低栄養
・認知機能の低下
これらの原因は相互に関係し合うのが特徴です。たとえば、慢性疾患によって疲れやすさがあり、動かなくなることで筋力が低下します。筋力が低下すると歩行スピードが落ち、外出が億劫になり、他者との関わりが減っていくでしょう。慢性疾患の影響で食事に制限がある場合も多く、うまく対応できずに低栄養となり、筋力低下・疲れやすさに拍車をかけるケースもよく見られます。
このように、フレイルの原因が悪循環を引き起こし、フレイルが進行していくことを「フレイルサイクル」と呼びます。
出典:兵庫県栄養士会
身体的にはフレイル状態にない高齢者も、社会的な側面でフレイルに該当する場合、4年後の身体的フレイルの新規発生リスクが3.93倍になるということが2018年に報告されました。社会との繋がりが希薄になることがフレイルの入り口であり、そこから身体的フレイル、認知的フレイルが進行するという考え方が「フレイル・ドミノ」です。
フレイルの進行を食い止めるためには、身体的・認知的・社会的な要因をそれぞれカバーしていくことが大切だといえます。
フレイルのチェックポイント
フレイルのチェックポイント
現在のところ、フレイルの診断基準として、統一された基準はありません。
身体的フレイルの代表的な診断方法としては、2020年に改定された「日本版CHS基準(J-CHS基準)」がよく用いられます。
項目 |
基準 |
体重減少 |
6か月で、2kg以上の意図しない体重減少がある |
筋力低下 |
握力:男性<28kg、女性<18kg |
疲労感 |
ここ2週間、わけもなく疲れたような感じがする |
歩行速度 |
通常歩行速度が<1.0m/秒 |
身体活動 |
① 軽い運動・体操をしているか? ② 定期的な運動・スポーツをしているか? 上記2つのいずれも「週に1回未満」と回答 |
上記の基準の3項目以上に該当する場合はフレイル、1〜2項目に該当する場合はプレフレイルです。
スクリーニングに用いる簡易評価法としては、「簡易フレイル・インデックス」や「FLAIL scale」などがあり、妥当性も示されています。
簡易フレイル・インデックス
|
|
回答 |
|
体重減少 |
6か月で2〜3kgの体重減少がありましたか? |
はい(1) |
いいえ(0) |
歩行速度 |
以前と比べて歩く速度が遅くなったと思いますか? |
はい(1) |
いいえ(0) |
運動 |
ウォーキングなどの運動を週に1回以上していますか? |
はい(0) |
いいえ(1) |
記憶 |
5分前のことが思い出せますか? |
はい(0) |
いいえ(1) |
疲労感 |
ここ2週間、わけもなく疲れたような感じがしますか? |
はい(1) |
いいえ(0) |
上記の質問の回答を点数化し、3点以上はフレイル、1点・2点をプレフレイルとします。
身体的問題だけでなく、多面的にフレイルの評価をするためのものとして、厚生労働省が作成した「基本チェックリスト」を用いることもあります。7領域・25個の質問に「はい・いいえ」で回答する自己記入式のチェックリストです。
フレイル予防の3つの柱+1
フレイル予防の3つの柱+1
フレイルは「可逆性」という特性を持っているため、予防に取り組むことが重要視されています。予防の3本柱は「栄養・運動・社会参加」です。それに加え、近年は心身の衰えに「お口の健康」も関わっているとわかってきました。
ここでは、口腔ケアを含んだ4つの予防策についてご紹介します。
栄養
高齢者は、摂取カロリー不足・栄養バランスの悪化が生じやすいです。「歳をとったから、粗食でよい」と考える方もいますので、フレイル対策に携わる方は、高齢者に対して適切な情報提供をおこないましょう。
低栄養がフレイルに関与するという複数の報告があります。ビタミンDなどのビタミン類、野菜、果物、魚の摂取量低下は、フレイル発症のリスク因子です。タンパク質の摂取に関しては、とくに高齢の女性ではフレイル発症リスクを下げる可能性が示唆されますが、タンパク質摂取だけでなく運動を併用することが推奨されます。
全体的な栄養バランスの改善策として、宅配食の利用や、冷凍食品・缶詰などの活用が挙げられます。高齢者のタンパク質摂取量を増やしたい場合は、フレイル対策に携わる方は今までの食事に「ちょい足し」を指導するとよいでしょう。チーズやヨーグルト、卵、納豆、豆腐などは、調理もほとんど不要で、誰でも追加しやすいです。
運動
筋力低下を防ぐためには、運動が必要不可欠です。高齢者は、加齢や持病が原因で関節の痛みや疲れやすさを感じるようになり、運動量が少なくなる傾向にあります。筋力が低下すると転倒・骨折のリスクも高くなり、要介護状態へ進展するきっかけとなってしまいます。また、体力の低下から外出が億劫になれば、社会的フレイルを加速させてしまうでしょう。運動は、フレイル予防の「肝」と言えます。
運動による身体運動機能やADLの改善効果は、重度のフレイルの方では効果が乏しいですが、軽度から中等度のフレイルの方には有効です。フレイルの発症・進行を予防するためには、レジスタンス運動(筋肉に負荷をかけて繰り返し行う運動)、バランストレーニング、機能的トレーニングなどを組み合わせたプログラムが推奨されます。
レジスタンス運動は、中等度の強度で8回1セットから開始し、3セットまで漸増するという方法がよいです。バランストレーニングとしては、手の支えなしに立ち上がること、障害物を避けながら歩くトレーニングなど、個々人の能力に応じて挑戦するようにします。
日常生活で取り入れられるようなトレーニングから始めてみましょう。たとえば、次のようなものは、体力に自信のない方でも取り組みやすいです。
・椅子の背もたれに軽く手をつき、かかとの上げ下ろし(10〜20回を1セット)
・椅子に浅く腰掛け、片足ずつ足をあげ5秒キープ(5〜10回を1セット)
・息が少し上がるくらいの早歩きでウォーキング
社会参加
日本では、社会的フレイルの頻度は8.4〜11.1%と報告されています。社会的フレイルの予防には、社会参加が重要です。
社会的フレイルの高齢者は、そうでない高齢者と比較して要介護となるリスクは1.66倍、死亡リスクが2.69倍と報告されています。人との関わりが減ったり、社会的な役割を失ったりすることは、認知機能の低下や抑うつ状態を引き起こす大きな要因です。
「社会参加」は、小さなことでもかまいません。近所の人や友人と話すこと、趣味のクラブ活動に参加すること、ボランティア活動に参加することのほか、家庭内で役割を持つこと(ゴミ捨て・掃除など)も、社会参加と言えます。
週に1回以上「誰かと交流する」かつ、月に1回以上「目的を持った活動に参加する」のが目安です。人との関わりを通じてさまざまな刺激を受けることができ、気持ちのハリが生まれます。
社会参加を促すための介護予防事業の一環として、厚生労働省が提唱しているのが「通いの場」です。各市町村や社会福祉協議会、NPO団体などが運営母体となっており、令和2年の段階で全国に113,886箇所設置されています。
口腔ケア
お口の健康が損なわれた状態を、「オーラルフレイル」と呼びます。咽せる、固いものが食べにくい、口が乾く、滑舌が悪い…などは、全て口腔機能の低下を反映した症状です。
・残歯が20本未満かつ咬合支持数9未満
・歯科受診をしていない
・口腔乾燥の自覚
などは、フレイルの関連因子として知られています。
オーラルフレイルは、身体的フレイルを引き起こす要因であり、口腔機能の維持・向上を目的に提案された日本オリジナルの概念です。フレイル予防のためには、定期的な歯科受診、適切な義歯の使用、口輪筋や舌のトレーニングなどを実施することをおすすめします。
口腔トレーニングは様々な方法がありますが、いくつかの例を紹介します。
・パタカラ体操(口や舌の動きをスムーズにする目的)
①「パ」…唇をはじくように
②「タ」…舌先を上の前歯の裏につけるように
③「カ」…舌の奥を上顎の奥につけるように
④「ラ」…舌をまるめるように
各発音 8回を2セット行いましょう
・開口訓練(飲み込む力をトレーニングする目的)
① ゆっくり大きく口を開け10秒間保持する。
② しっかり口を閉じて10秒間休憩する。
1日2セット(朝・夕)行う。
※お口を開くときには、無理せずに痛みが出ない程度にしてください。
・早口言葉(滑舌をよくする目的)
レベル1:生麦、生米、生卵
レベル2:隣の客は、よく柿食う客だ
レベル3:青巻紙、赤巻紙、黄巻紙
レベル4:隣の竹垣に竹立てかけたのは、竹立てかけたかったので、竹立てかけた
※口を大きく開いて3回連続で発生しましょう。
病気のケアや服薬の見直しもフレイル予防につながる
病気のケアや服薬の見直しもフレイル予防につながる
フレイルには、持病やその治療薬も関わっています。医療従事者も十分に理解して、高齢者へ理解を求めること、適切な介入を行うことが大切です。
持病のコントロール
さまざまな疾患がフレイルと関連します。フレイルの発症・悪化予防のためには、疾患のコントロールも必要です。
たとえば、糖尿病はフレイルの発症リスクを増加させ、また、フレイルが糖尿病の発症リスクを増加させます。低血糖もまた、身体機能の低下をきたすことから、フレイルのリスクを上昇させる可能性があり、血糖の適切なコントロールは重要です。心不全、急性冠症候群、心房細動といった心疾患を持つ患者のフレイル頻度は高く、予後悪化にも関連します。
患者が慢性疾患の治療の必要性を理解し、前向きに治療を継続するためには、医療従事者のサポートが不可欠です。
薬の副作用やポリファーマシーに注意
薬剤数の増加がフレイルと関連することは、複数の報告から明らかにされてきました。一般的に、薬剤数が7以上の場合はフレイルのリスクが高いと判断します。
疾患の治療に必要不可欠な薬剤も多くあるため、一概に薬剤数を減らすことがよいとは言い切れませんが、副作用・相互作用・服薬管理などの状況を総合的に評価し、処方を適正化することを意識する必要があるでしょう。
とくに、処方カスケード(服用薬による有害な反応が新たな病状と誤認されてしまい、新たに薬が処方されること)は是正を目指したいところです。ある薬剤の副作用に対して、治療のためにさらに薬を処方するという連鎖現象を指します。薬の必要性、副作用の可能性を吟味することが、フレイル予防につながります。
感染症の予防
高齢者は、感染症にかかることをきっかけとして、慢性疾患の悪化や筋力低下などを容易に引き起こし、急速にフレイルが進行してしまうことが少なくありません。感染そのものだけでなく、感染による社会的孤立や精神的なダメージも、認知機能や心の健康に影響を与えます。
そのため、日頃から手洗い・うがい、適度な換気、ワクチン接種などをおこなって感染症の予防に努めることも、フレイル予防として重要です。インフルエンザ、肺炎球菌、帯状疱疹など、高齢者のワクチン接種には自治体からの助成を受けられる場合もあります。適切な情報提供で、感染予防を促していきましょう。
【メディカル ジャパン】では、フレイル予防、
介護予防器具、未病・予防製品、リハビリ用品などが出展します。
フレイル予防に向けた取り組み事例
フレイル予防に向けた取り組み事例
フレイル予防のために、実際におこなわれている取り組み事例をご紹介します。これからフレイル予防に取り組もうとされる皆さまの参考になれば幸いです。
大阪府八尾市:ご当地体操、スマホ/タブレット活用講座
大阪府八尾市の「八尾市健康まちづくり計画」では、フレイル予防をテーマにさまざまな取り組みをしています。
高齢者が自身の体の状態を把握するための「介護予防体力測定会」は、市内在住の65歳以上の方なら無料で参加できるイベントです。握力や開眼片足立ちによる運動機能評価、栄養状態の評価、反復唾液嚥下テストなど、本格的な項目を測定できます。
さらに、「健康づくり出前講座」と題して、川内音頭・ノルディックウォーキング・わかわかごぼうトレーニングなど、八尾市オリジナルのトレーニングを実際におこなう機会も設定しています。
大阪府公式アプリ「アスマイル」、独立行政法人東京都健康長寿医療センターが作成した「スクワット・チャレンジ」「運動カウンター」など、アプリの活用も積極的にすすめています。スマートフォンやタブレットを使ってポイントを貯めたり、他の利用者との「競い合い」をしたりと、楽しみながらフレイル予防ができる仕組みです。
八尾市に限らず、多くの自治体がフレイル予防のハンドブック作成や、運動教室の開催などに取り組んでいます。
神奈川県横浜市:フレイル予防薬局の活用
横浜市と横浜市薬剤師会が協力し、市民のフレイル予防の推進をはかるため、「フレイル予防薬局」を認証する事業を展開しています。フレイル予防に関する情報提供や助言指導を、身近な医療機関である薬局で実施するという取り組みです。
フレイル予防薬局として認証されるためには、次のような要件が設けられており、1年単位での更新となっています。
・フレイル予防の取り組みを常時実施可能
・月1人以上の住民に取り組みを実施
・健康サポート薬局を届け出ている
高齢者の「ファーストアクセス」の場として機能するだけでなく、必要に応じて医療機関や介護サービス事業所と速やかな連携が取れる点も、薬局活用の利点といえるでしょう。
自治体とトレーニングジムとの連携
トレーニングジムを運営するRIZAP株式会社は、いくつかの自治体と「フレイル予防」を軸とした健康増進事業を2023年から実施しています。トレーニングだけでなく、行動変容を促すためのノウハウもあり、長期的な効果が期待されるでしょう。
実際に以下のような取り組みがおこなわれています。
・食事や運動に関するフレイル予防動画の配信
・健康セミナーの開催
・官民連携のコンビニジムの設置やジムを活用した運動習慣づくり
・スマートフォンアプリを使用した食事記録とアドバイス
・ライブ配信型の運動講座の開催
・医療や介護の専門職に対するワークショップの実施
ライブ配信型の講座というのが、ライザップ株式会社によるフレイル予防の特色の1つです。
2022年に実施されたRIAP株式会社・株式会社JDSC・ユカイ工学株式会社の3社合同実証では、デバイスを使用したオンラインによる運動指導でも、フレイルリスクの低減や、運動習慣の定着が見られました。今後、さまざまな自治体でも、対面の通いの場だけでなく、オンラインを活用したフレイル予防の取り組みが増えていくのかもしれません。
まとめ・展示会のご紹介
まとめ・展示会のご紹介
今回は、「フレイル予防」に着目し、フレイルそのものや、予防のために必要な取り組みについてご紹介してきました。健康寿命の延伸のために欠かせない取り組みであり、今後はさらにその必要性が高まってくるでしょう。
メディカルジャパンは、介護・福祉・未病に関するさまざまな製品・サービスが集まる展示会です。フレイルチェックに役立つ機器などをお探しの方は、ぜひご来場ください。
【メディカル ジャパン】では、フレイル予防、
介護予防器具、未病・予防製品、リハビリ用品などが出展します。
監修者情報
監修:松繁 治(マツシゲ オサム)
プロフィール:
岡山大学医学部卒業 / 現在は新東京病院勤務 / 専門は整形外科、脊椎外科
免許・資格:
日本整形外科学会専門医
日本整形外科学会認定 脊椎脊髄病医
日本脊椎脊髄病学会認定 脊椎脊髄外科指導医
日本整形外科学会認定 脊椎内視鏡下手術・技術認定医
著書、論文:
ガイドワイヤーを用いない経皮的椎弓根スクリュー(PPS)刺入法とその長期成績
所属:
新東京病院
専門領域:
医療 > 外科 > 整形外科
▼この記事をSNSでシェアする