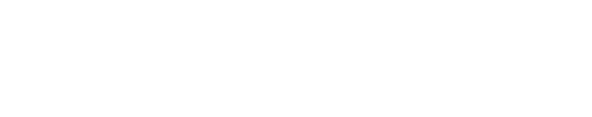生活習慣病の予防はこの5つ!今日からできる対策と年代別のポイントを解説
40代頃になると、生活習慣病を意識する方も増えてきます。「健康的な生活を送りたい」と思っていても、具体的にどうすればよいかわからない人も多いのではないでしょうか。この記事では、生活習慣病予防の5つの柱(食事、運動、睡眠、節酒、禁煙)を中心に、年代や性別に応じたポイント、自治体の支援策もあわせてご紹介します。
【予防1】食事バランスを整える
【予防1】食事バランスを整える
「バランスのよい食事」は健康の基本です。しかし、どのような内容が理想的なのか、実感をもてない人も多いのが現状です。
意識と現実のギャップ:あなたの食生活、本当に健康ですか?
農林水産省の調査によると、「日ごろから健全な食生活を心がけている」と答えた人は75.9%にのぼります。全年代で女性の方が健康的な食生活に対して意識は高いですが、40代以降は男女ともに60%以上の方が食生活に気を配っているようです。
しかしその一方で、実際の栄養摂取状況には、理想とのギャップがあるのも事実です。とくに「野菜不足」と「塩分のとりすぎ」は、代表的な課題としてあげられます。次の表で、目標値と現状の差を確認してみましょう。
<表:摂取状況と目標値の比較>
項目 |
実際の平均 |
推奨目標 |
理想とのギャップ |
野菜摂取量 |
約250g |
350g以上 |
約100g不足。特に若年層で不足傾向。 |
食塩摂取(男性) |
10.7g |
7.5g未満 |
目標値を大きく上回る |
食塩摂取(女性) |
9.1g |
6.5g未満 |
男性よりは少ないが、依然として多め |
<表:摂取状況と目標値の比較>
項目 |
実際の平均 |
推奨目標 |
理想とのギャップ |
野菜摂取量 |
約250g |
350g以上 |
約100g不足。特に若年層で不足傾向。 |
食塩摂取(男性) |
10.7g |
7.5g未満 |
目標値を大きく上回る |
食塩摂取(女性) |
9.1g |
6.5g未満 |
男性よりは少ないが、依然として多め |
このように、「気をつけているつもり」でも、実際の食事内容には改善の余地があるケースが少なくありません。
健康的な食生活を送るためのポイント
生活習慣病を予防するためには、特定の食品を控えるだけでなく、必要な栄養素をバランスよく摂取すること、その食生活を長く継続することが大切です。以下のポイントを意識してみましょう。
POINT 1. 主食・主菜・副菜の「定食スタイル」を目指す
一品料理ではなく、主食・主菜・副菜を揃えた定食スタイルで食事を用意してみましょう。たとえば、「朝食はトーストとコーヒーだけ」という方は、ゆで卵とミニトマトを足してみると、少しバランスがよくなります。
また、厚生労働省と農林水産省が共同で作成した「食事バランスガイド」を用いて、自分の食事バランスをチェックするのもおすすめです。
POIONT 2. 減塩を意識する
日本人は、世界的にみても食塩の摂取量が多いです。塩分のとりすぎは高血圧の原因になるため、減塩はどの年代でも取り組んでいきたいポイントといえます。
簡単に取り入れられるのは、減塩調味料(減塩醤油、減塩味噌など)の活用です。自宅にある調味料を減塩の商品に変えるだけなら、難しくありません。また、ポン酢やケチャップ、マヨネーズは、醤油に比べ、一般的に塩分が低いです。たとえば、冷奴を食べる時に醤油ではなくポン酢を使うなど、「調味料の置き換え」も、1つの方法です。
POINT 3. 野菜を1日350g以上とる
野菜を積極的にとりましょう。キャベツやほうれん草などの葉物野菜だけでなく、海藻、きのこなども野菜に含まれます。
あまり自炊をしない方でも、工夫次第で野菜の摂取量を増やすことは可能です。たとえば、冷凍の野菜(ほうれん草、ブロッコリー、オクラ等)を、購入したサラダや味噌汁などに加えてみてはいかがでしょうか。
POINT 4. アプリで食事管理をおこなう
食事の内容を登録するだけで、栄養バランスのチェックや摂取カロリーの計算をしてくれるアプリがいくつもあります。アプリを活用することで、栄養士などからの専門的な指導がなくても、簡易的に食事内容の改善点を探すことが可能です。「あすけん」「YAZIO」など、使いやすいものを探してみてください。
【予防2】運動を習慣化する
【予防2】運動を習慣化する
40代、50代は仕事や家庭に忙しく、「食事は気をつけていても、運動までは…」という方も多いです。しかし、生活習慣病の予防には、運動習慣も欠かせません。
運動不足の実態:日本人の運動習慣は?
「令和5年国民健康・栄養調査」によると、運動習慣がある人(週2回以上・30分以上の運動を1年以上継続している人)の割合は、男女ともに約30%前後にとどまっており、この10年間横ばいの状態です。若い年代の方ほど運動習慣が少なく、60代・70代では運動習慣のある方が増えていることがわかりました。
また、1日あたりの平均歩数は、男性で6,600歩、女性で5,600歩程度と、目標とされる8,000歩には届いておらず、年々減少傾向にあります。近年、在宅勤務・テレワークが進みつつあることも、歩数の減少に関与しているのかもしれません。
年代別運動の目安:無理なく続けられる運動を見つけよう
生活習慣病予防のためには、ジムに通ったり、スポーツチームに参加したりといった本格的な運動は必須ではありません。「日常に取り入れやすく、継続できる運動」を習慣化するのがポイントです。以下に、年代ごとに推奨される運動の目安をまとめました。
<表:年代別の運動の目安>
年代 |
運動量の目安 |
運動の内容・ポイント |
その他の注意点 |
18〜64歳 |
週に4メッツ・時以上(例:週1時間の中強度運動) |
・汗をかいて息が弾む程度の運動 |
長時間の座りっぱなしは避ける。30分ごとにこまめに立ち上がることが重要 |
65歳以上 |
毎日40分以上の身体活動+6,000歩以上 |
・有酸素運動(ウォーキング等)、筋力トレーニング、バランス運動を組み合わせることを推奨 |
体力に自信があれば18〜64歳と同等の運動も可 |
<表:年代別の運動の目安>
年代 |
運動量の目安 |
運動の内容・ポイント |
その他の注意点 |
18〜64歳 |
週に4メッツ・時以上(例:週1時間の中強度運動) |
・汗をかいて息が弾む程度の運動 |
長時間の座りっぱなしは避ける。30分ごとにこまめに立ち上がることが重要 |
65歳以上 |
毎日40分以上の身体活動+6,000歩以上 |
・有酸素運動(ウォーキング等)、筋力トレーニング、バランス運動を組み合わせることを推奨 |
体力に自信があれば18〜64歳と同等の運動も可 |
※メッツ・時:身体活動量を表す単位。座って安静にしているときの状態を1メッツ、普通歩行を3メッツなどと定義し、その数値に運動時間をかけたもの。
継続のコツは、成果を目に見える形で表すことです。
・アプリの活用
歩数を記録するアプリを活用することで、取り組みが可視化され、やる気につながります。
・カレンダーに記録し家族に共有
歩数・運動をしたかどうかなどをカレンダーに記録し家族にも共有することで、「サボらずに頑張ろう」という気持ちを維持しやすくなります。
また、ちょっとした身体活動を習慣化するのも有効です。
・階段を使う
エレベーターではなく階段を使うようにするだけで、身体活動量が増えます。
・少しの距離は歩く
ごく近場の場合は電車や車を使わず、歩くようにしてみましょう。
【未病・予防・健康EXPO】では、生活習慣病予防をはじめ、
未病・予防医療・介護予防・健康増進に関する製品・サービスが多数出展します。
【予防3】質のよい睡眠を確保する
【予防3】質のよい睡眠を確保する
「最近、なんだか疲れが取れない」「夜中に何度も目が覚める」そんな悩みを抱えている方は少なくありません。睡眠は、心身の健康を保つうえで欠かせない基本習慣のひとつです。
睡眠不足は現代病?あなたの睡眠時間、足りていますか?
「令和5年国民健康・栄養調査」によると、1日の平均睡眠時間が6時間未満の方の割合は、男性で38.5%、女性では43.6%にものぼります。「ここ1か月、十分な睡眠を取れている」と答えた方の割合は、年々減少傾向です。
人により最適な睡眠時間は異なりますが、成人では6〜8時間を目安とすることが厚生労働省により推奨されています。高齢者の場合、床上時間(ベッドに入っている時間)が8時間を超えないことが目安です。床上時間が長すぎると、死亡率が高くなると報告されています。
じつは、睡眠不足は、糖尿病・高血圧・肥満など生活習慣病のリスクを高める要因としても知られています。また、ストレスが多いと交感神経が優位になって睡眠の質が下がり、日中の疲労感や集中力の低下を招き、生活の質全体に影響を及ぼすという悪循環の原因でもあります。日々の睡眠の見直しは、よりよい生活のための必須事項です。
今日からできる快眠習慣
忙しい毎日の中でも、ちょっとした工夫で睡眠の質を高めることは可能です。
POINT 1. 寝る前の行動を見直す
寝る直前のスマートフォンやパソコンの使用は、ブルーライトの影響で脳が覚醒しやすくなることが知られています。就寝の30分前にはデジタル機器をオフにし、リラックスする時間を作るのがおすすめです。また、カフェインの摂取も眠りの質に影響を及ぼすため、夕方以降は控えるようにしましょう。
POINT 2. 環境を整える
快適な睡眠環境づくりも重要です。寝室は暗く静かで、適度な湿度(50〜60%)と温度(夏は26℃前後、冬は18℃前後)を保つように心がけましょう。エアコンや加湿器の活用も有効です。
POINT 3. 睡眠中央時刻をずらさない
就寝時刻と起床時刻の中央である「睡眠中央時刻」が、平日と休日で大きくずれている方は要注意です。睡眠中央時刻がズレると「ソーシャルジェットラグ(社会的時差ボケ)」と呼ばれる体内時計の乱れが引き起こされ、健康を損なうリスクになることがわかっています。長く寝たい日は、いつもより「早寝遅起き」を心がけましょう。
【予防4】飲酒量を見直す
【予防4】飲酒量を見直す
「適度な飲酒は健康によい」と言われることもありますが、その「適度」がどの程度か理解していますか?最近は、少量の飲酒でもがんや高血圧などの生活習慣病リスクが上昇するという報告も出てきました。嗜好品としてお酒を楽しみつつ健康を守るために、「飲み方」を見直すことが大切です。
お酒との上手な付き合い方
生活習慣病のリスクを高めない量の飲酒を「適量」とすると、1日あたりの純アルコール摂取量は以下の量が目安です。
男性:40g未満
女性:20g未満
「純アルコール20g」とは、どのくらいの量なのかを具体的に見てみましょう。
<表:純アルコール20gに相当するお酒の量>
お酒の種類 |
目安量(20g相当) |
ビール |
500ml(中瓶1本) |
日本酒 |
180ml(1合) |
焼酎 |
110ml(グラス半分程度) |
ウイスキー |
60ml(ダブル1杯) |
案外、少ないと感じるのではないでしょうか。これよりも多く飲酒している方の割合は、男性14.1%、女性9.5%であり、女性はやや増加傾向です。
週に3日以上の「休肝日」を設けることで、がんや死亡のリスクを抑えることができると報告されています。休肝日を設けつつ、飲酒量も減らしていきましょう。
【予防5】禁煙への一歩を踏み出す
【予防5】禁煙への一歩を踏み出す
令和5年の「国民健康・栄養調査」によると、喫煙者の割合は男性25.6%、女性6.9%で、ここ10年ほどは年々減少してきています。とはいえ、まだ禁煙の決意ができていない方、禁煙がうまくいかない方は多いです。
禁煙のメリットと始め方
タバコは血管や肺へダメージを生じさせ、動脈硬化による心筋梗塞や脳梗塞、肺がんなどのリスクを高めます。
禁煙は、何歳からでも遅くありません。たとえば、禁煙後すぐに血圧や脈拍が安定し、数日後には味覚や嗅覚が改善します。1年後には肺の機能が改善し、5年後には肺がんのリスクが大きく低下、10年後にはさまざまな疾患のリスクが非喫煙者と同等にまで近づくのです。
禁煙外来やニコチン代替療法、アプリなどを活用することで、成功率が大きく上がります。「やめたい」という気持ちを大切に、できることから始めてみましょう。
年代・性別で異なる生活習慣病予防のポイント
年代・性別で異なる生活習慣病予防のポイント
生活習慣病予防の考え方、意識の仕方は、年代や性別によっても変わります。
20〜30代|生活習慣の基礎づくり
まだまだ生活習慣病とは無縁な年代だと思われがちですが、予防のための健康的な生活習慣は、若いうちからの積み重ねが大切です。バランスよく食べ、運動をおこない、よく眠るという「生活の基礎」を固める時期としましょう。
40〜50代|健診結果をきっかけに予防強化を
健康診断で「血圧やコレステロールが高い」と指摘される人が増えてくる年代です。数値の変化を見逃さず、生活習慣を見直すタイミングとして活用しましょう。自覚症状がなくても、放置せず、対策をとり始めることが大切です。
60代以上|健康寿命を延ばす“無理のない継続”がカギ
加齢とともに少しずつ身体機能は衰えていきます。健康のための習慣も、「無理なく継続する」ことが大切です。体調に合わせた運動をおこない、食事のバランスも考えましょう。
男性|内臓脂肪・高血圧・脂質異常に要注意
男性は内臓脂肪型肥満(いわゆるメタボ)になりやすく、40代以降はとくに注意が必要です。塩分・脂質を摂りすぎないよう食事内容に気を配る、体重測定の習慣をつけるなど、意識して過ごしましょう。
女性|更年期以降のホルモン変化に備えた栄養・骨・睡眠ケア
女性は、女性ホルモンであるエストロゲンによって健康が維持されています。そのため、閉経前後は、骨密度の低下、血圧やコレステロール値の上昇、動脈硬化の進展による心筋梗塞のリスク上昇など、さまざまな健康問題を生じやすい時期です。若いうちから栄養を十分にとり、運動習慣をつけることが、更年期以降の健康維持に繋がります。
予防習慣と一緒に活用したい!自治体の支援策を知ろう
予防習慣と一緒に活用したい!自治体の支援策を知ろう
国や自治体も、生活習慣病予防には力を入れています。
健康マイレージ制度
代表的なのが、全国の自治体や企業、健康保険組合が提供するウォーキング支援サービス「健康マイレージ制度」です。スマホアプリや歩数計で日々の運動量を記録し、ポイントとして貯めると、抽選やクーポンなどの特典が受けられます。楽しみながら健康づくりができる制度として、注目されています。
禁煙支援アプリ&禁煙外来費用の補助
禁煙を成功させるには、ひとりで頑張るのではなく、周囲の支援を得ることが大切です。
近年では、禁煙支援アプリを活用する人も増えています。アプリでは、禁煙日数や節約金額の可視化、他ユーザーとの励まし合いなどができ、継続のモチベーションにもつながるでしょう。
また、お住まいの自治体によっては、禁煙外来の費用を一部助成している場合もあります。まずは、自治体の公式ホームページなどで情報を確認してみてください。
予防を怠ると…生活習慣病は“サイレントキラー”
予防を怠ると…生活習慣病は“サイレントキラー”
生活習慣病は、「サイレントキラー」と呼ばれることがあります。サイレントキラーと呼ばれる理由や、進行した場合のリスクについてご紹介します。
なぜ「気づかぬうちに進行する」のか?
高血圧や糖尿病、脂質異常症などの生活習慣病は、血管や臓器にじわじわとダメージを与えていきます。しかし、それ自体では痛みやだるさなどの症状がほとんどありません。そのため、忙しさや「まだ大丈夫だろう」という油断から、医療機関へ行かずに終わってしまう人も少なくないのが現実です。
自覚症状がないため危機感を持ちにくく、対応せずに放置していた結果、気が付かないうちに進行してしまうのです。
代表的な生活習慣病と放置した場合のリスク
代表的な生活習慣病について、放置するとどのようなリスクがあるのかお伝えします。以下の表に、主な病気とその特徴、放置した場合に起こりうる健康リスクをまとめました。
<表:主な生活習慣病と放置した場合のリスク>
病気名 |
主な原因・特徴 |
放置した場合のリスク |
高血圧 |
塩分過多、運動不足、遺伝など |
動脈硬化、脳卒中、心筋梗塞 |
糖尿病 |
食生活の乱れ、肥満、ストレスなど |
神経障害、腎不全、失明 |
脂質異常症 |
脂質摂取過多、運動不足など |
血管の詰まり、狭心症、心筋梗塞 |
<表:主な生活習慣病と放置した場合のリスク>
病気名 |
主な原因・特徴 |
放置した場合のリスク |
高血圧 |
塩分過多、運動不足、遺伝など |
動脈硬化、脳卒中、心筋梗塞 |
糖尿病 |
食生活の乱れ、肥満、ストレスなど |
神経障害、腎不全、失明 |
脂質異常症 |
脂質摂取過多、運動不足など |
血管の詰まり、狭心症、心筋梗塞 |
これらの病気は、「自覚症状がほとんどないまま進行する」という点が共通しています。異常を指摘された場合は放置せず、早めの対処を心がけましょう。
まとめ・展示会のご紹介
まとめ・展示会のご紹介
今回は、生活習慣病から大きな疾患へ進行するのを予防するために、一人ひとりができる取り組みについてご紹介しました。食事・運動・睡眠などを見直すほか、自治体の取り組みに参加するのもよいでしょう。
メディカルジャパンでは、「未病・予防・健康」に関するさまざまな商品を比較検討することが可能です。健康増進のためのウエアやサプリメント、フィットネス機器、健康管理デバイスなどの取り扱いがあります。生活習慣病予防に取り組みたいと考えている方は、ぜひご来場ください。
【未病・予防・健康EXPO】では、生活習慣病予防をはじめ、
未病・予防医療・介護予防・健康増進に関する製品・サービスが多数出展します。
監修者情報
監修:本多 洋介(ほんだ ようすけ)
経歴:
群馬大学医学部卒業
伊勢崎市民病院、群馬県立心臓血管センター、済生会横浜市東部病院(いずれも循環器内科)を経て、Myクリニック本多内科医院院長。
免許・資格:
・総合内科専門医
・循環器内科専門医
・日本心血管インターベンション学会専門医
・軽カテーテル的大動脈弁植え込み術指導医(Sapienシリーズ、Evolutシリーズ)
所属:
Myクリニック本多内科医院 院長
専門領域:
・医療 > 内科 > 消化器内科
・医療 > 内科 > 腎臓内科
・医療 > 内科 > 総合内科
・医療 > 内科 > 循環器内科
・医療 > 内科 > 糖尿病内科
▼この記事をSNSでシェアする